🌟新着🌟スマホの利用料はだれが払うのがふつうなのですか?

高校生のときのスマホの利用料はだれが払うのがふつうなのですか?
そうた 高校1年生
音声で聴く

先輩たちからのメッセージ

「里親家庭で生活しています」
匿名 / 母子生活支援施設・乳児院・児童養護施設・里親家庭経験、大学生
詳しく見る
スマホの利用料は、里親さんが支払っていましたが、クレジットカードが作れる年齢(18歳)の時に私が支払う形に変わりました。

「自分で払っていました」
レモン / 乳児院・児童養護施設・里親家庭経験、短期大学2年生
詳しく見る
普通やどれが正解とかはないと思いますが、一つの例として私は自分でアルバイトして貯めたお金でスマホを買い毎月の支払いも自分でしていました。
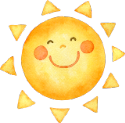
「私のいた施設では」
ゆきあ / 児童養護施設経験、大学2年生
詳しく見る
私は児童養護施設で生活していましたが、自分の貯金から引き落としで支払いしていました。
里親家庭と児童養護施設では違うところがあると思いますが、児童養護施設では自分で使った分は自分で支払う、という形を取っているところが多いと思います。

「里親さんが支払ってくれていました」
ななみ / 里親家庭経験、福祉系大学2年生
詳しく見る
私の場合は里親家庭で、スマホの利用料は里親さんに払ってもらっていました。
詳しくは分からないですが、里親さんに養育費として支給されているお金などから支払われていたと思われます。

「一つの施設の中でもいろいろ」
匿名 / 児童養護施設経験、大学2年生
詳しく見る
私はスマホを持ち始めた高校生の時から、自分で払っています。
高校生の時は施設からの小遣いをためて払いました。
施設の周りの子は親に払ってもらうのが当たり前でしたが、私は母子家庭で兄弟も多いため、母に負担をかけてスマホを使用するのは罪悪感があったので、それなら自分で払って好きなように使おうと思ってきました。

「施設内で差がでないための決まり」
たくま / 児童養護施設経験、専門学校2年生
詳しく見る
自分の場合は、必ず寮(施設)による契約で、自宅からの持ち込みは禁止でした。(ギガや機種などに個人で差が生まれて嫉妬や盗難など色々防ぐため)
支払いは貯めた小遣いの中から自分で払うって感じでした!
里親の場合は里親の方と話して決めるのがいいと思います!

「自分で払って、結果的によかった」
匿名 / 乳児院・児童養護施設経験、専門2年生
詳しく見る
私の施設のルールは、高校1年生からスマホを持つことができ、スマホ代は自分でバイトをして支払うというものでした。
部活が忙しかったり、事情があってバイトができないなどの一部の子は親や施設が負担していたと思います。
私自身は、高校3年生まで施設にいて今は親と一緒に暮らしています。
高1から現在に至るまで料金の支払いは自分で行なっています。
高校生のときは自分で支払っているのを偉いとか思ってたりもしましたが、普通の家庭でも自分で支払ってるという友達もいて、そんなことはないんだなって思いました。
どちらが普通とかはないと思いますが、私的には、自分で支払いをしていたほうが、自分のお金の使い方を考えることができてよかったと思います。

「養育者の方とすり合わせを」
ふうね / 里親家庭経験、大学2年生
詳しく見る
契約は里親さん名義でしてくれますが、携帯代は自分でアルバイトをして支払っていました。
個人的にお小遣いだけではまかなえないと思います。
高校生になる前に施設職員さん、里親さん、児相職員さんのいずれかから説明があると思うので、情報のすり合わせをしましょう。

大人からのメッセージ

「よく話し合って、納得いく形を」
詳しく見る
個人使用のスマホは、利用する本人が利用料を支払うのが普通のようですが、施設や里親家庭には、それぞれルールがあると思います。スマホの利用料金をだれが払うかについても施設や里親家庭によって違います。
児童手当(令和6年10月以降の中高校生:第1子・第2子は月1万円、第3子以降は一律月3万円)が、18歳まで支給されるようになったので、それを使って支払うことも可能ですし、アルバイトなどをして支払う場合や、里親さんが負担したり、実親さんが購入して子どもに渡している場合もあります。
施設によっては、施設長が貸し与える場合も見受けられますが、利用料は本人から徴収されているようです。
スマホ利用に関しては、施設や、里親さんとよく話し合いをして、納得のいく支払方法を見つけてください。そうしてお互いにルールを守ってトラブルがないようにしたいものですね。
因みに、スマホ里親ドットネットの2019年に東京・神奈川・埼玉・千葉県所在の児童養護施設調査では、高校生全体のスマホ所持率は98%と、ほぼすべての子が高校生になるとスマホを持っているのに比べ、児童養護施設の子ども達のスマホの所持率は69.3%と低くなっています。スマホの利用料金は「全額を高校生が自分で支払う」が同調査において最も多く87%となっています。

「国の指針もあります。まずは話し合いましょう」
詳しく見る
2022年10月、厚生労働省が児童養護施設に指針を文書で通知しました。
指針では「携帯電話等はさまざまな情報にアクセスするための通信手段や緊急連絡手段として、日常生活において有用なものとなっている」と指摘して、日常生活の利用を目的にする場合は措置費のうちの「一般生活費」、オンライン授業などを目的にする場合は「特別育成費」などから支出することが示されています。
一方、スマホの所持を推奨する内容ではなく「所持するかどうかも含め、子どもの年齢、利用頻度、閲覧の制限など、各施設において適切に判断いただきたい」としています。
以上の指針はありますが、スマホの料金の支払いについては施設や里親さんによって違いがありますので、かかる金額などについて職員や里親さんに相談してみてください。
